インプラントの基礎知識
当院採用の
インプラントメーカーについて

くまがい歯科では1997年以降、ドイツ製のAnkylos Implant systemsを採用しており、2022年までは全体の95%を占めます。
1996年以前はスイス製のStraumann® のティッシュレベルインプラントを採用していました。
そして2023年より同社の最新のボーンレベル BLX Implant systemsがラインナップに加わり、特に臼歯部においては現在主流となっています。
さらに2025年からは特に上顎の臼歯部で副鼻腔が低位のため、インプラント埋入部の垂直骨量が数mmしかない難易度の高いケースに於いて、今までは2回以上の高侵襲の手術と完了まで1.5年ほどの期間を要していた複雑な副鼻腔内骨造成手術をせずに、30分ほどの低侵襲の手術で数カ月と短期間で治療が完了する特殊な手術技法とそれに適したMEGAGEN社のワイドショートインプラントを導入し、今まで手術の大変さと長期間要する事でインプラントを諦めていた方にもご期待に添えるようになりました。


インプラント治療を受けられた患者さんは、ご自分のインプラントの情報を把握しておかれる事をお勧めします。
インプラントは世界中で100種類以上存在し、日本国内では40種類ほどが使われています。
いつの間にか、消えていったインプラントもあり新旧入れ替わりも激しいです。
不便なのは、インプラントメーカーによって規格が異なり、パーツや工具の互換性がほとんどありません。
また、同じメーカのインプラントであっても、種類やサイズによりパーツや工具が異なることは普通にあります。
インプラントに関わるトラブル症例で、患者さんがそれらを施術した医師との折り合いが悪くなり転医されて来られるケースが多々あります。
そのような場合、前医からの情報が得られない事例が多く、X線写真でのシルエットと僅かな露出部分の形状からインプラントの種別を特定しなければなりません。
形状のよく似たインプラントが多々あり、ましてや複数のメーカーが混在していたりすると特定までにひと月も費やした事例もありました。
他院施術のインプラントトラブルのリカバリーは、その専用工具を取りそろえる事が第一歩です。
過去に姿を消したインプラントでは、種別の特定が困難な上にパーツや工具を入手出来ないものも多々あります。そうなると他メーカーのパーツを流用加工するなどの工夫が必要となり、そのような技術以前の理由で難症例となってしまいます。
当院ではそのようなケースでも可能な限り温存を試みますが、それは労力と手間暇がかかるため、大学付属病院等ではそのような複雑なインプラントは撤去するのが基本となっているようです。
しかし、感染等で周囲骨がほとんど破壊されているようなケースを除き、数mmでも骨とインテグレーションしたインプラントは天然歯のようには簡単に抜去できません。
その場合はインプラント周囲の骨を全周削って分離するなどの手法が一般的ですが、周囲骨のダメージが避けられませんので、患者さんにとっては実にお気の毒な話です。
当院にて主に使用しているAnkylosはドイツではNo1のシェアで世界中で評価されているインプラントであり、パーツの供給が無くなるような心配はありません。 他の2メーカーについても同様です。
当院でインプラント治療の終了した患者さんには、使用したインプラントや上部構造についての詳細を記した書類をお渡ししています。 同時に上部構造の修理に有効な作業模型も保管していただいています。
インプラントの構造


インプラントには、1ピースと2ピースのタイプのものがあります。
1ピースは文字通りのシンプルな構造で、顎骨内に埋入する部分と、クラウンを被せる部分が一体で、埋入後のクラウン装着までの手順は天然歯の修復と近似しています。
2ピースは顎骨内に埋入するフィクスチャーとクラウン等の上部構造を支えるアバットメントで構成されます。
アバットメントは、スクリューでフィクスチャーに装着する構造で、前歯に適した形状、臼歯に適した形状、ブリッジ用、義歯を支えるアタッチメントの付与されたもの、角度のついた物等、様々な種類やサイズが選択出来ます。
当初は1歯のインプラントだったのが、隣の歯が抜歯となりインプラントを追加埋入したような場面では、ブリッジ用のアバットメントに交換して、連結した上部構造にリニューアルしたり設計を変更することなどが容易です。
又、欠損歯数が大幅に拡大して、インプラントの上部構造のクラウンだけでは歯列が構成しきれないような場合には上部構造をアバットメントから取り外して、義歯の保持用アタッチメント付きのアバットメントに交換することにより、可撤式のアタッチメント義歯を製作する事も可能です。
或いは、歯肉上に露出しているアバットメントのみをドライバーで容易に撤去する事で、インプラントは自然と歯肉の下に埋もれるので、あたかも何もしていない白紙の状態に戻す事も出来ます。
1ピースのインプラントだとこれらの改造が一切できません。


当院で主に使用しているAnkylos Implant systemsのアバットメント
2ピースインプラントにはティッシュレベルとボーンレベルの2タイプがあります。
ティッシュレベルは骨内の部分と歯肉を貫通する滑沢な部分からなるフィクスチャーです。
ボーンレベルはフィクスチャー全てが骨内に埋入されます。
ティッシュレベルは1ピースインプラントと同じく軟膜組織下に接合部を持たないことから、フィクスチャーとアバットメント間のマイクロギャップによる周囲組織の炎症が生じません。
ボーンレベルタイプでは、歯肉の厚みに合わせたアバットメントの選択や、カスタムメイドのアバットメントにより歯肉縁下から上部構造を形作ることが
出来るので、前歯の歯肉ラインの審美的再現にも適しています。
当院で現在、主に使用しているAnkylosはすべてボーンレベルインプラントです。

ティッシュレベル ボーンレベル
エクスターナルコネクションとインターナルコネクション
2ピースインプラントでのフィクスチャーとアバットメントの連結システムには2タイプあります。
1つは近代のチタン製インプラントのパイオニアであるスウェーデンのBrånemarkに代表されるエクスターナルコネクションです。
フィクスチャーの凸凹部にアバットメントの凸凹部を嵌合させる構造で、それのみには機械的維持はありません。
フィクスチャーとアバットメントの連結維持はスクリューに依存するため、スクリューの緩みや破損が弱点です。
もう1つはインターナルコネクションで、フィクスチャー内部にアバットメントを嵌め込む構造です。
その中でも、筒状のテーパーシリンダー内に円錐状のアバットメントをテーパー嵌合させ楔効果により強固に固定するシステムをモーステーパーロッキングコネクションと言い、これは30年以上前にAnkylosで採用されたシステムです。


エクスターナルコネクション

インターナルコネクション
イラストはBrånemark
イラストはAnkylos
モーステーパーロッキングコネクションの、モーステーパーはBICONの1.5度からAstrateckの11度、又、あるものは15度と各社様々です。11度となると嵌合力は弱くなり、スクリューの緩むケースが出てきます。
モーステーパーの角度が小さい程、フィクスチャーとアバットメントの機械的結合力が強くなります。
その反面、アバットメントの挿入方向の許容角度が小さいのでアバットメント一体型の上部構造を中間歯欠損部に作製するような場合は、フィクスチャーの埋入角度が斜めだと上部構造が臨在歯にぶつかって入りませんので、技術的難易度は高くなります。
BICON Ankylos Straumann® Astrateck

1.5度 5.7度 8度 11度
各社で異なるモーステーパー
エクスターナルコネクションにおいては咬合圧によってアバットメントのマイクロモーションが生じ、それによるフィクスチャーとアバットメント連結部にマイクロギャップが生じ、汚染される事でその辺縁骨がさら状に吸収してレベルダウンしてしまうケースが多発しています。
それをソーサライゼーションと言い、Brånemarkのバットジョイントシステムの大半に生じています。
その点、1ピースインプラントやティッシュレベルインプラントでは骨レベルに接合部が無いので、その様な事例は生じません。
現在はインターナルコネクションのシェアが主流になってきましたが、インプラントの埋入角度を適切に出来ないとスクリューリテインによる上部構造の作製が困難なため、埋入角度を選ばないエクスターナルコネクションの需要もまだあります。


ソーサライゼーション
(マイクロギャップ内の汚染による、さら状の辺縁骨の吸収)
エクスターナルコネクションの マイクロギャップ
くまがい歯科で1997年以降採用しているAnkylos Implant systemsは
2ピースのインターナルコネクションインプラントです。
Ankylosは20年間の追跡調査にて98%以上の存続率である事が公表されています。
1987にリリースされ、今、世界で最も長期経過の優れたインプラントとして、先発メーカーまでもそのシステムを取り入れるようになっています。
Ankylos の存続率がTOPのKeyPointは
★インターナルモーステーパーロッキングコネクション
★プラットホームスイッチング
★骨縁下埋入
★インターナルモーステーパーロッキングコネクション

モーステーパー
(Ankylosは5.7度)
アバットメントとフィクスチャーとの結合は、モーステーパーロッキングコネクションと呼ばれるインターナルコネクションです。
モーステーパーロッキングコネクションは、モーステーパー角が小さい程機械的結合力が強くなります。
Ankylosはモーステーパーが5.7度と小さく、嵌合力が強固でアバットメントのマイクロモーションやマイクロギャップを生じないので骨吸収(ソーサライゼーション)を明らかに減少させることが臨床により裏付けられました。
★プラットホームスイッチングと
★骨縁下埋入

フィクスチャ―とアバットメントの接合部分を“プラットフォーム”と言います。
そして、アバットメントの外径をフィクスチャ―より一回り小さくしたものがプラットフォームスイッチングです。
又、Ankylosの、他のインプラントシステムには無い手法として、骨縁よりも1~2mm深く埋入する事が推奨されています。
プラットフォームスイッチングではインプラント本体とアバットメントの接合部で段差ができるのですが、その段差部分を包み込むように骨が再生してきます。
さらにアバットメントの歯肉縁下部分のくびれ部分の歯肉の厚みが増すことで血流量も増します。
インターナルモーステーパーロッキングコネクションによるギャップフリーの効果もあり、Ankylosは骨吸収と歯肉の退縮が最も少ないインプラントだと評価されています。
上部構造の装着様式
セメント固定
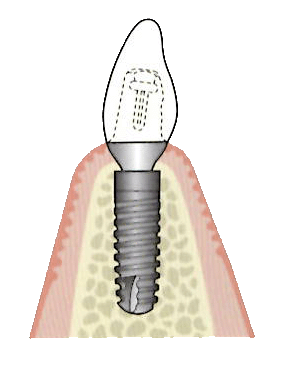
天然歯にクラウンをセメントで接着するのと同じように、アバットメントにクラウンを接着して固定する方法です。
しかし、外すことを前提にせず強固に接着してしまうと、撤去する際にクラウンを破壊しなければならないので、当院でセメント固定する場合は、インプラント専用のリムーバルセメントにて可撤式にしています。
これにより、チェックや修理の際に上部構造を容易に取り外すことが出来ます。
但し、壊さずに取り外すことが前提ですので、経年により接着が緩むことがあります。
もしセメントの耐久劣化により自然と脱落した場合は、速やかに来院いただき、同様に仮着いたします。
もし、何らかの事情で他院でつけてもらう場合は、仮着でとお願いしてください。
その際、通常の天然歯用のリムーバルセメントは被膜が厚く、その分咬み合わせが高くなってしまう事があるので、インプラント専用のリムーバルセメントの使用が望ましいです。
スクリューリテイン
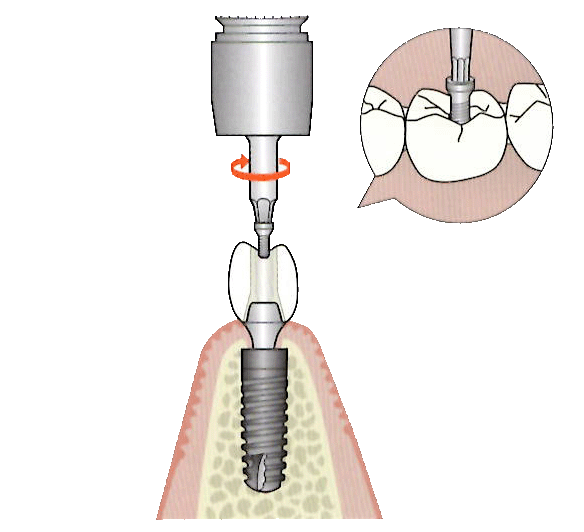
セメントを一切使用しないで、スクリューにて固定する方法です。
残留セメントによる骨や歯肉への悪影響も無く、リペア―やチェックの際には上部構造を傷つける事無く外すことが出来ます。
当院では、可能な限りスクリューリティンを採択しています。
スクリューを締結するトルクは、その使用パーツ毎に適正トルクが指定されています。
トルクが強すぎると、スクリューが破損したり、弱いと緩んだりするので規定値を順守する事が大切です。
トルクコントロールラチェットやトルクインジケーター付きのラチェットを使用して正確に締結します。
以上は代表的な固定法ですが、他にテレスコープクラウンのような物理的嵌合により接着剤を使用せずに固定する方法や、弾性アタッチメントにより患者さんご自身で脱着する方法等あります。
複数歯の連結されたインプラント上部構造を固定する場合、当院が特に気を遣っている事があります。
それは上顎骨の柔軟性を阻害しないという事です。
特に正中口蓋縫合の可動性を制限しないように設計をします。
ですから、近年よく見られる"All on 4" 或いは "All on 6"を上顎には行いません。
そのような場合は、上部構造をセパレートしたり、弾性材アタッチメントにて患者可撤式にする等の設計を検討します。
その理由につきましてはこの👇リンクボタンからご覧ください。

